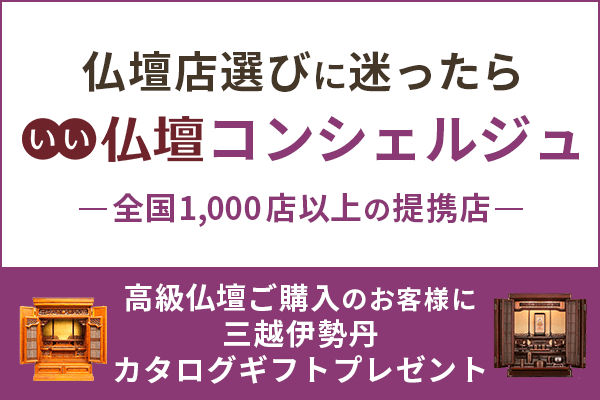おりんというのは、仏壇に置かれ、専用の棒で叩くと甲高く澄んだ音が出るお椀のような形をした仏具です。小さいころ楽器のように何度も鳴らして怒られたことがある、という方もいるのではないでしょうか。
この道具の呼び方は宗派によって少し違いますが、ここでは「おりん」や「りん」と呼びます。おりんはなんのためにあるのか、正しく鳴らす方法とは、どのような種類があるのかなどを説明していきますので、おりんを選ぶ際の参考にしてください。
仏壇には必ずと言っていいほど、おりんが置かれています。楽器のように叩くと音が鳴りますが、おりんは楽器ではなく正式な仏具ですので、丁寧な取り扱いが必要です。
おりんは梵音具のひとつ
おりんは、音を出す仏具・梵音具(ぼんおんぐ)の一種です。木魚やお寺の鐘なども梵音具に属します。
家庭用のものと寺院で使用されるものは違い、寺院用のものは磬子(「けいす」または「きんす」)と言われ、色が黒く縁がとても厚く作られています。
おりんは「リーン」「チーン」と可愛らしい音が鳴りますが、磬子は「ゴーン」という低い音が響きわたります。
宗派で呼び方が違うおりん
もともとは禅宗で使われていた仏具ですが、現在はすべての宗派で使用されています。
漢字では「鈴」や「輪」と表されますが、すずと区別をつけるために「りん」や「リン」のようにひらがなやカタカナで表記されることが多いです。
名前の呼び方は宗派によって少し違いがあり、日蓮宗などは鈴(りん)、天台宗や浄土真宗では鏧(きん)、浄土宗では小鏧(しょうきん)、そのほかは、鐘(かね)と呼ぶこともあります。
おりんは叩くととても澄んだ美しい音を響かせるのが特徴で、その音は極楽浄土の仏様の耳にまで届くといわれています。
また人々の邪念を払うともいわれており、仏様や先祖、故人への純粋な祈りや供養の心を、澄んだ音にのせて伝える役割を担っています。
おりんの歴史
お釈迦様が亡くなられた時「りん」という鳥が悲しんでいたことから、その「りん」の鳴き声に似た音色を再現するために作られたのが、おりんの由来であると言われています。
日本における起源は、禅宗にあると言われています。坐禅や瞑想の勤行の際に、その開始や終了の合図として使用されていたようです。その後、寺院での読経や修行の場で、広く利用されるようになっていきました。
おりんの種類
おりんにはその用途や使用する場面に合わせて、さまざまな種類があります。
おりんそのものは宗派による決まりがありませんが、おりんを置くりん台やりん布団に決まりのある宗派もあるので、どのような種類のものがあるのか知っておくと便利です。
鉢型
基本的なおりんの形で、鉢や壺のような見た目をしています。
おりんのりんとは、お椀型の鐘の部分のことを指し、おりんを鳴らすためにはりん棒と呼ばれる専用の棒が必要です。
またリンを直接仏壇に置くのではなく、りん台と呼ばれる台の上に置くのが一般的で、さらにリンの衝撃を吸収して傷がつくのを防ぐために、間にりん布団と呼ばれる中敷きを敷きます。
昔ながらのおりんのスタイルで、りん、りん棒、りん布団、りん台がセットになっているタイプのものです。
印金(いんきん)
持ち手がある小型のおりんとりん布団を手に取り、りん棒で音を鳴らすおりんです。
携帯用のおりんで、お墓での法要の際などに僧侶が使用することが多いです。
ハンドベルのような見た目をイメージすると分かりやすいと思います。
高台りん
ワイングラスのようにりんに脚が付いたタイプのおりんで、りん台を必要としません。
りん自体に脚がついているので、衝撃を吸収するためのりん布団を使用する必要はありませんが、下敷きとして薄いりん敷きを敷くことが多いです。
そのほか豊富なバリエーションあり
おりんはそのサイズや形状、素材によってさまざまなバリエーションがあります。
昔ながらの鉢型に加えて、最近では一見おりんだと分からないようなお洒落なものも増えてきています。
おりんは宗派によっては指定される場合もありますが、特別なことがない限り比較的自由に選択できる仏具ですので、希望の叶うデザインや音色のおりんを選択するのもよいでしょう。
おりんの鳴らし方
おりんはいつ、どのように鳴らすのが良いのか分からない、という方も多いのではないでしょうか。
線香を立てたあと仏様に手を合わせる前におりんを鳴らし、そのあと合掌するという流れをよく目にしますが、鳴らし方にはマナーがあり、むやみやたらに鳴らして良いものではありません。
おりんを鳴らす意味や役割をきちんと理解して鳴らすことが大切です。

読経の際に鳴らす
おりんは厳密にいうと経本を読む際に使用するもので、一定の区切りをつけるため、また、音程とリズムを合わせるために鳴らします。
読経を始める前、読経の最中、そして読経の終わりに鳴らすのが一般的で、それ以外は基本的に鳴らす必要はないとされています。
鳴らすタイミングや回数は宗派によって多少違いがありますが、それぞれの区切りで鳴らす箇所がしっかり指示されています。
仏壇に手を合わせるタイミングで鳴らす
家庭の仏壇での日常礼拝としては、「お参りにきました」「これから供養します」という意味を込めて、手を合わせる前におりんを鳴らします。
また、仏壇に朝のご飯やお供えものをお供えするときにも、「お供えをします」「召し上がってください」という気持ちを込めておりんを鳴らし、合掌をしてご挨拶をします。
ただ、線香をあげて合掌するだけのときはおりんを鳴らさない、という宗派もあるので、不明な場合は菩提寺に確認するとよいです。
正しい打ち方で鳴らす
おりんを鳴らす際は、りん棒の持ち手の端の方を親指と人差し指と中指でつまむように持ち、りんの縁を打ちます。
リンはどこを打っても音は鳴りますが、基本的には上から叩くように打つのではなく、横からリンの縁に沿って軽く弾ませるように打ちます。縁の外側を叩くと澄んだ音になり、内側を叩くと柔らかい音になります。
宗派によってはリンの内側を叩く場合もあるので、ご自分の宗派やお寺の打ち方で鳴らすようにします。
おりんを鳴らす回数
先にも述べたように、鳴らす回数は宗派によって違います。
例をあげると、読経前・最中・終わりでそれぞれ2回・1回・3回、または2回・2回・3回などがあり、同じ宗派でもお寺によって違うこともあります。
一般家庭では特に回数は決められていませんが、仏壇の前に座り手を合わせる前に1~3回を目安に鳴らすと良いでしょう。
宗派によるおりん選びの注意点
おりんは比較的自由に選ぶことができる仏具なので、基本的に選び方に決まりはありませんが、浄土真宗の場合は指定があるので注意が必要です。
浄土真宗本願寺派
浄土真宗本願寺派では、六角形型または丸型のりん台を使用します。
六角形型または丸型のりん台の上に、りん布団を置き、その上に鉢型のおりんを置きます。
浄土真宗大谷派
浄土真宗大谷派のりん台は、四角形型のものを使用します。
本願寺派と違いりん布団は使用せず、代わりに金襴輪(きんらんわ)という輪をりん台の上に置き、その上にりんを置きます。
金襴輪は中心が空洞になっている仏具で、金襴が巻き付けられているのが特徴です。
おりんを選ぶ際のポイント
おりんを鳴らした時に、その音色が心地良く聞こえるかどうかはおりん選びのとても大切なポイントです。
また、おりんを置く仏壇とおりんとの、大きさやデザインのバランスが取れているかどうかも考慮したい点です。
音色で選ぶ
おりんの音色は、大きさ、形状、厚み、製法で違いが生まれます。おりんはなんといってもその澄んだ美しい音色が特徴的な仏具なので、選ぶ際の音色の良し悪しはとても重要です。
音を鳴らしてみたとき音割れがなく、余韻が長く続き、静かに消えるものを選ぶようにしましょう。
また音色には聞く人の好みもあるので、ご自身が心地よいと感じるものがよいでしょう。

仏壇のサイズやデザインに合わせる
おりんの大きさは7cm~15cmのものが主流ですが、最近では小型の仏壇用のおりんや、近代的でスタイリッシュなタイプのおりんも多く揃っています。
お寺でよく見かけるオーソドックスなおりんから、あまり場所をとらずに置けるタイプなど、さまざまな種類のおりんがありますので、仏壇のサイズやデザインに合わせて選ぶと良いでしょう。
おりんのお手入れ方法
おりんは長く使っていると当然汚れてきますし、錆が付いてくることもあります。おりんは仏具なので、丁寧にお手入れをして大切に扱う必要があります。
表面に着色やメッキの加工がされている場合は柔らかい布で優しく磨きます。くすんできた場合は、専用の艶出し剤を使用すると、元の色を取り戻すことができます。着色やメッキの加工がないものであれば、研磨剤を使用する方法も効果的です。
ここでご紹介するのは、家庭内での手入れ方法です。少しでも取り扱いに不安がある場合は、仏壇仏具店に相談することをおすすめします。
研磨剤を使用する場合
研磨剤はホームセンターなどで取り扱っている金属磨き用のものか、専用のクリーナーを仏壇仏具店で購入することをおすすめします。
新聞紙や柔らかい布に研磨剤を付け、おりん全体にまんべんなく塗ります。
優しく磨き、研磨剤が汚れで黒ずんできたら、乾いた布で拭き取れば完了です。
おりんが傷まないように、素材をよく確認してから研磨剤を使用してください。
錆にはお酢
錆を落とす方法として、お酢を使う方法もあります。
やり方はいたって簡単で、料理用のお酢におりんを浸けておくだけです。
しばらく浸けておくと錆が浮いてお酢が黒ずんでくるので、錆がとれたらよく水洗いをすれば完了です。
ひどい汚れは業者に依頼
あまりにも劣化や汚れがひどい場合は、専門の業者に依頼するのも一つの手です。
ただし、そこまで汚れがひどくなる前に、日々のお手入れをなるべくこまめに行うことを心がけてください。
おりんはどこで購入できるのか
仏壇・仏具店のほか、通信販売、ホームセンターなどで取り扱っている場合もあります。
通信販売の場合、おりんを専門に取り扱っているところもありデザインも豊富ですが、やはり直接ものを見て購入することをおすすめします。
仏壇・仏具店で相談する
仏壇・仏具店は、仏具を専門的に取り扱っているので、宗派や仏壇のサイズ、予算などの相談ができるので安心です。
おりんを選ぶ際は、その音色も重要なポイントになるので、可能であれば実際に鳴らして音を聞かせてもらうとよいでしょう。
どんなものを購入したらよいか迷ったときは、お近くの仏壇・仏具店で専門的な知識を持った方に相談してみてはいかがでしょうか。
また、最近では金や銀など貴金属で作られた高価なおりんも販売されています。この場合、取り扱っているお店が限られているので、希望される方はあらかじめ調べてからお求めになってください。
ご自身にあったおりんを選びましょう
おりんの役割や種類、鳴らし方などを説明してきました。
おりんの澄み渡った美しい響きは私たちの心を清らかにして、極楽浄土にいる仏様やご先祖様、故人に祈りや供養を届けてくれる大切な役割を担っています。また、人々の邪念を取り払う効用もあると言われています。
おりんは目にする機会の多い仏具で、鳴らすと誰でも簡単に音を出すことができますが、だからこそその役割や意味をよく理解して使用することが大切です。
おりんは仏壇・仏具店などで購入することができます。仏壇・仏具店で購入する場合は「いい仏壇」の割引クーポンを利用することもできますので、ぜひ、ご利用ください。