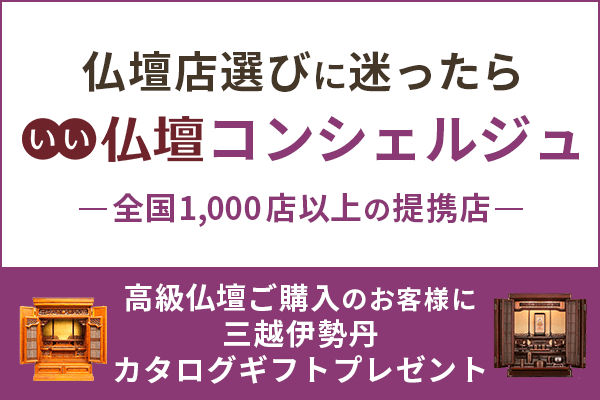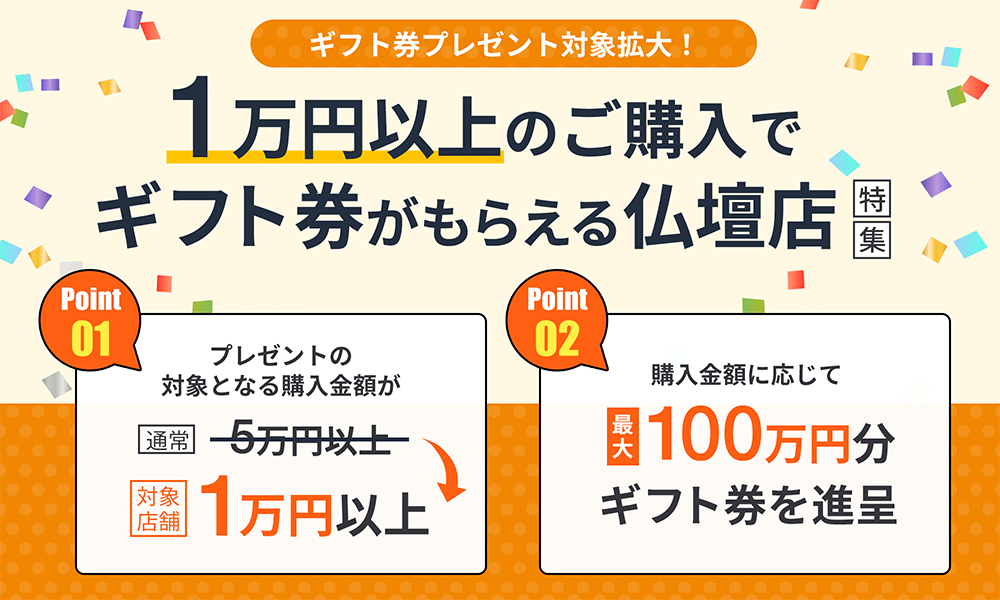香炉は、お線香を焚く時に使用する器のことで、灯供養具や花供養具と並ぶ重要な香供養具です。
三具足、五具足のいずれにおいても必要な仏具であり、その香りは私たちの心身を浄化してくれるものとも考えられています。
しかし、香炉は種類も多く、適切なものを選ぶにはそれなりの知識が必要です。
そこで今回、香炉とはどのようなものなのか、その種類や使い方、選び方などについて紹介したいと思います。

後悔しないお仏壇選びのための総合カタログプレゼント!後悔しないお仏壇選びのための総合カタログプレゼント!
- 購入する時の注意点とは
- 価格・サイズ・設置例を詳しく
- 我が家にぴったりのお仏壇とは
- お仏具の役割やお飾りの仕方
- ご安置のポイント
- お仏壇Q&A
- お仏壇選びステップガイド
- リビングルームにあうカタログ
香炉とはお香を焚くために使う器のことで、仏壇にお祀(まつ)りする仏具の中のひとつです。
宗派や地域の風習によって使用する香炉に違いがあり、用途も若干の違いがあります。
香炉は、灯明(燭台)、花瓶(花立て)などの仏具と共に三具足(五具足)のひとつに位置づけられています。
また、元々は仏具だったのですが、香道や部屋の調度品などにも用いられるようになりました。
材質は陶磁器や金属製、漆器などが一般的です。
お香を入れる器である「香盒(こうごう)」と合わせて、本式のものを揃えたいところです。
香炉の歴史
香炉発祥の地は、日本ではなく海外とされています。
仏教起源の地である古代インドには、香りを焚く風習がありました。
その理由は、インドの気候やスパイスの文化によるようです。
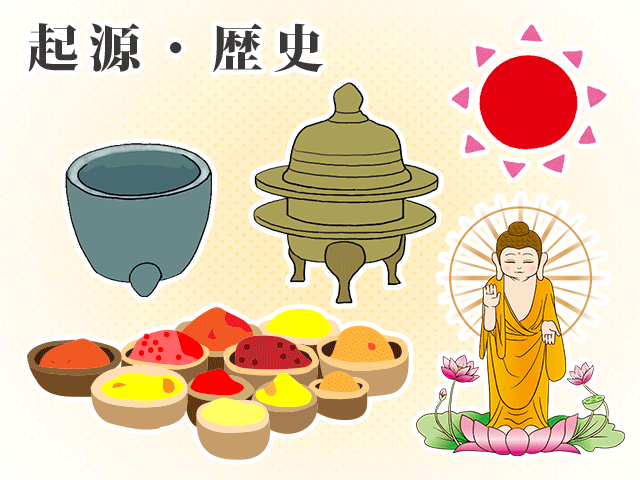
一年を通して気温が高く、スパイス王国であるインドでは、悪臭を防ぐためにさまざまな香料をブレンドしたお香を体にまとう風習があったとされています。
その文化がギリシャやエジプト、ローマへと伝わり、いっぽうアジア圏では、古代中国や朝鮮を経て日本にも伝来しました。
日本への伝来については、奈良時代の歴史書『日本書紀』に、595年に香木が淡路島に漂着したことが残っています。漂着した香木は、島の住人が香木と知らずに燃やしてしまいました。しかし、非常に良い香りがしたため、驚いてすぐに朝廷に献上したというエピソードが記されています。
「法隆寺」が所蔵する飛鳥時代の真鍮製の「柄香炉(えごうろ)」が現存する日本国内最古の香炉といわれています。
その後、桃山時代には、茶道と共に様式も徐々に整備され、江戸時代初期には香道の大まかな流れが完成し、庶民にも浸透していったということです。
香炉の種類・使い方
実に種類が豊富な香炉。
代表的な香炉としては、下記が一般的です。
- 前香炉
- 土香炉(玉香炉/透かし香炉)
- 火舎香炉
- 長香炉
これらの香炉は用途別にさらに2種類に分けられます。
- 線香を立てる際に使用する仏壇用
- 法事などでお焼香をするための焼香用
それぞれの特徴や使い方について説明したいと思います。
前香炉
最も代表的な香炉といえるのが、前香炉です。
特徴としては、下記の通り。
- 主に浄土真宗以外の宗派で使われる
- 仏壇仏具店などで最も多いタイプの仏壇用香炉
一般的には、マッチ消しや線香立、経本、ロウソク消しなどと一緒に経机に置き、中に香炉灰を敷き詰めて線香を立てるために使用されます。
3本足のものは、1本の足の方を手前に向けて置きます。
地域によって、線香炉や机用香炉などと呼ばれる場合もありますが、経机やスライド式の膳引きなどに置いて線香を立てる用途で使われることから、このように呼ばれています。
また、大型の仏壇の場合は、経机の上に置きます。いっぽう、小型や経机がない仏壇の場合は、最下段かスライドさせた膳引きの上に置くことが多いです。
土香炉(玉香炉、透かし香炉)
土香炉は、浄土真宗系の仏壇用香炉です。
特徴としては、下記の通り。
- 主に浄土真宗で使われる
- 青磁の香炉が一般的な仏壇用香炉
- 宗派によって細かく分類される
浄土真宗で使われる香炉には、土香炉以外に金属製の金香炉があります。
土香炉は主に一般家庭、金香炉は寺院などで使われます。
また、「浄土真宗で使われる香炉は土香炉」とひとくくりにされがちですが、
- 浄土真宗本願寺派では「玉香炉」
- 真宗大谷派では「透かし香炉」
と呼ばれるなど厳密には違いもあります。
実際、仏壇仏具店でも各宗派の名称で販売されています。
使い方に関しては、浄土真宗では線香を立てないため、土香炉に2~3回折った線香を横にして焚きます。
火舎香炉
火舎香炉は、浄土真宗系で焼香用に使われる真鍮製の香炉です。
煙出しの穴が付いた蓋が印象的な香炉です。
3本足のため、1本の足の側を手前に向けて置きます。
使い方は、上卓の中央に置き、左右には華瓶を置きます。
仏壇仏具店などでは、火舎華鋲セットとして販売されることも多いです。
また、焼香用では火舎香炉以外に、焼香用角香炉(しょうこうようかくこうろ)を使用することもあります。
焼香用角香炉は、右にお香、左には灰と香炭を入れて使用します。
墓地で法要を行う際は、手提げが付いているタイプのものを使用します。
長香炉
長香炉は線香を縦に寝かせて供えるタイプの仏壇用香炉です。
伝統型の大きな仏壇に合わせた黒檀調や紫檀調のものが多いですが、実際はあまり使われることはないようです。
香炉の選び方
香炉を購入する際、宗派や地域ごとの風習、仏壇の大きさに合わず使えないというケースも少なからずあります。
そこで、香炉を選ぶ際の注意点を説明します。
宗派や地域ごとの風習で選ぶ
先ほども少し触れましたが、宗旨・宗派によって使われる香炉は異なります。
例えば、浄土真宗では、線香を寝かせるかたちで焚くため、土香炉を使用します。
また、神道の場合は線香をあげないため、玉串をお供えします。
従って、香炉自体が不要です。

宗派によって、線香の本数や手向け方が異なるため、それに合わせた香炉を選ぶ必要があります。
また、宗旨・宗派だけでなく、地域によっても線香のあげかたが異なる場合もありますので、お寺や仏壇仏具店などにあらかじめ相談するとよいでしょう。
予算
香炉の値段はさまざまで、特にこだわりがなければ、安いものでは数百円のものから、有名な陶芸家の手掛けたものであれば10万円以上するものまであります。
香炉の相場として数千円後半から数万円程度を目安に、ご自分の目的や予算に合わせて選ぶのがよいでしょう。
サイズ
香炉のサイズも重要なポイントです。
仏壇の大きさや、置き場所を考慮した上で、線香を立て安い高さのものを選ぶことが重要です。
五具足、三具足とは
五具足、三具足とは、仏壇に荘厳する(飾る)基本的な仏具を合わせた総称です。
具体的には、香炉とロウソクを立てる燭台、そして花瓶を一対ずつ祀る形式を「五具足」と呼びます。
また、香炉と燭台、花瓶それぞれひとつずつ祀る形式は「三具足」と呼びます。
それぞれが、香供養、花供養、灯供養のために使われる大切な仏具です。
正式な荘厳は「五具足」とされていますが、通常は「三具足」で荘厳する場合が多く、お仏壇の大きさや菩提寺の考え方、地域の慣習などによって変わってきます。
なお、浄土真宗本願寺派では、「三具足」または「五具足」を前卓に祀り、「四具足」と呼ばれる一対の華瓶(けびょう)、火舎(かしゃ)、燭台の4点を本尊に近い上卓(うわじょく)に用いる「四具足」が正式とされていす。
具足については、こちらで詳しく解説しています。

香炉灰、香炉石とは
ここでは、香炉とセットで使う「香炉灰」と、最近注目されている「香炉石」について説明します。
香炉灰の種類
香炉を使う場合、線香を立てるために必要な香炉灰。
香炉灰には、さまざまな種類がありますが、一般的なものは下記の通り。
- 珪藻土灰
- 藁灰
- 菱灰(ひしばい)
最も一般的なものが、植物性プランクトンが化石化した自然素材の珪藻土を使った「珪藻土灰」です。
次に、藁を燃やした灰で作った「藁灰」は、軽くて通気性もよく線香が燃え残りにくいため、線香を立てるのに適しています。
また、「菱灰」と呼ばれる、菱の実の殻を焼いた灰もよく使われます。
相場としては、珪藻土灰が最も安価で、菱灰が最も高いと覚えておきましょう。
香炉灰の使い方
前述したように香炉灰は、香炉を使う際、そのままでは線香が刺さらないため、香炉の中に灰を敷き詰めて安定させることで、刺さるようにするためのものです。
珪藻土(けいそうど)や珪砂(けいさ)、藁(わら)などの灰を香炉に入れ、そこに線香を立てて使用します。
また、前香炉の場合は、中に香炉灰を敷き詰めて線香を立てます。
香炉に灰を入れることによって安定するため、線香が倒れたり、風で燃えカスが散ってしまったりするのを防ぐことが可能です。
香炉灰の購入方法
香炉灰は、仏壇仏具店やホームセンター、最近では100円ショップなどで購入が可能です。
もちろん、ネット通販でも購入できます。
販売店では、香炉とセット販売されていることが多いです。
香炉灰に代わる香炉石のメリット
最近、洗って繰り返し使える香炉石が注目されています。
線香を立てるのに必須の香炉灰ですが、お手入れが面倒だというデメリットもあります。
そこで、手入れが簡単な香炉石のニーズが高まってきました。
例えば、香炉灰は風で舞ってしまったり、誤って香炉をひっくり返してしまったりした際の掃除が大変ですが、香炉石はそういった心配もありません。
さらに、天然石などは、カラフルなものも多いため、見た目にも美しい点がメリットです。
このような理由から、最近ではモダン仏壇など仏壇のデザインに合わせて香炉石を使う方も増えているようです。
香炉のお手入れ方法
香炉は使っているうちに、線香の燃えカスなどで香炉灰が汚れてしまいます。
ですので、定期的に香炉灰の掃除をする必要があります。
掃除手順は大まかに3工程に分けられます。
- まず、箸などで線香の燃え残りやカスを取り除く
- 次に、新聞紙などの上で、灰ふるいを使って灰をこし香炉に戻す
- 最後に、灰ならしを使い、表面を綺麗にならして終了
香炉灰を使用するなら、こまめなお手入れを心がけましょう。
香炉で焚くお香の種類と使い方
香炉で焚くお香にも、さまざまな種類があります。
ここでは、代表的なものと使い方を紹介します。
線香
家庭などで使われる一般的な線香です。宗派や風習によって焚き方が異なりますが、香炉の中に3方向に1本ずつ立てることが多いです。
長い線香
座禅香とも呼ばれる、非常に長い線香です。禅堂用では70センチ以上もの長さとなり、大型の香炉に立てて使われます。法要の導師用として使用されることが一般的です。
短い線香
10センチ未満の短いものもあり、仏事用というよりはフルーツや花、スパイスの香りなど、いろいろな香りを楽しむものが一般的です。
宗派・地域に合わせて香炉を選ぼう
仏壇において重要な仏具の1つである香炉について、さまざまな種類やルールなどがあることをご理解いただけたかと思います。
しかし、すぐにすべてを理解するのは難しいと思いますので、購入を検討される際は、お寺や仏壇仏具店などにも相談することおすすめします。
プロの意見も参考にして、あなたにとって最適な香炉を見つけていただければと思います。

後悔しないお仏壇選びのための総合カタログプレゼント!後悔しないお仏壇選びのための総合カタログプレゼント!
- 購入する時の注意点とは
- 価格・サイズ・設置例を詳しく
- 我が家にぴったりのお仏壇とは
- お仏具の役割やお飾りの仕方
- ご安置のポイント
- お仏壇Q&A
- お仏壇選びステップガイド
- リビングルームにあうカタログ
仏具や位牌でもギフトをもらえるチャンス!1万円以上のご購入でギフト券がもらえる仏壇店特集
特集店舗では、1万円以上の商品を購入した方に最大100万円分のギフト券をプレゼントしています。 ※通常店舗は5万円以上の購入からプレゼント。
5万円未満の仏具や位牌でもギフトをもらえるチャンス!ぜひ、ご利用ください。