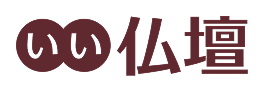金剛杵とは

金剛杵(こんごうしょ)とは?
仏像や肖像画で弘法大師空海の右手に握られた小さなバトン状の法具をご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。チベット仏教を国教に定めているブータン王国の紋章には、中央に十字を象った金剛杵がデザインされています。
金剛杵の基本的なデザイン
金剛杵の種類と名称
もっともよく知られている独鈷杵は東大寺の金剛力士像(仁王像)が肩に担いでいるものです。もともと金剛力士にはサンスクリット語で「金剛杵を持つ者(ヴァジュラダラ)」という意味があります。
鈷は、大型の魚を射る漁具の銛(もり)が変形したものといわれ、その先端は垂直に伸びる「中鈷」の周りを、湾曲した「脇鈷」が取り囲んでいます。
同じ金剛杵でも、片方の鈷が爪ではなく鐘になったものを金剛鈴(こんごうれい)と呼び、やはり鈷の数によって独鈷鈴(とっこれい)、三鈷鈴(さんこれい)、五鈷鈴(ごこれい)のように呼び方が変わります。
爪の数は中鈷を中心に「三鈷杵・五鈷杵・七鈷杵・九鈷杵」と奇数を刻んで増え、フォークのような形をした「三鈷杵」は、祈る者の三業と仏の「三密(身・口・意)」を、「五鈷杵」であれば大日如来の「五智(法界体性智・大円鏡智・平等性智・妙観察智・成所作智)」を表すとされています。
ちなみに、高野山の観光スポットである「三鈷の松」は、本来2本一組の松の針葉が3本一組で生えてくるのが特徴ですが、むかし唐から戻った弘法大師が密教の教えを広めるのにふさわしい地を求めて三鈷杵を東の空に投げたところ、高野山の松の木に掛かったとの言い伝えが残っています。
金剛杵の用途とは?
仏教には大きく「顕教」と「密教」に分かれています。おもに経典や念仏などで広く誰にでも明らかにされる教えが「顕教」であるのに対し、教えの奥深さゆえ一般人には明かされず、師から弟子へと秘密裏に受け継がれていくのが「密教」だとされています。
密教の起源はインド仏教
金剛杵のモデルは雷神の武器
密教における金剛杵では、基本の形である「独鈷杵」がもっとも重要視されているとの説と、弘法大師空海がいつも手に持っていた「五鈷杵」こそが重要であるとの説がありますが、秘儀であるだけに正確なことは定かではありません。
まとめ
仏壇についての疑問のほか、お墓や葬儀に関わるお悩みがあれば、いい仏壇までお問い合わせください。