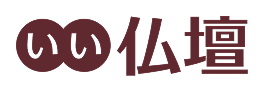仏具の選び方

仏壇は本来、本尊をおまつりし、仏教徒として仏様に手を合わせる場所です。本尊やご先祖を供養すると共に、感謝の気持ちを育むものとして神聖な気持ちになれる、後世に引き継がれていくべきものでもあります。
仏具の種類
主な仏具の種類・仏具の意味
本尊(ほんぞん)
仏壇(ぶつだん)
香炉(こうろ)
香合(こうごう)
ろうそく立て(燭台)
仏教ではろうそくは仏様の「知恵」を意味し、ろうそくを灯すことによって、仏様の大いなる知恵でわれわれ愚かな人間を導いてくれるとされています。
*ろうそくの炎を消すときは、手のひらをうちわのようにして風を送って消すか、ろうそく消し用のうちわで消すのが作法です。決して息を吹きかけて消してはいけません。仏教では、人間の息は不浄だとされているためです。
花立て
浄土真宗では華瓶(けびょう)といい同じハナの瓶ですが、使い方は全く違います。
仏飯器・仏器(ぶっぱんき・ぶっき)
炊き上がりの最初のご飯をよそい、食べ物の命をありがたく感謝していただく気持ちで拝んでから食事をします。できれば毎日お供えすることが望ましいです。
茶湯器(ちゃとうき)
こちらも仏飯器・仏器同様に毎日お供えすることが望ましいです。
*浄土真宗ではお供えしません。
高坏(たかつき)
おりん
*梵音具(ぼんおんぐ)とは音を鳴らす仏具のこと。
リーンという澄んだ音によって人々の邪念を払い、祈りや供養を仏様の住む所まで届くように打ち鳴らします。
りん台、りん布団、りん棒などとセットで使われます。
木魚(もくぎょ)
木柾(もくしょう)
灯篭(とうろう)
ろうそくと同じ、仏様の「知恵」を表し、灯すことによって人間の煩悩を打ち消すとされています。
宗派により、吊り下げるタイプと置くタイプがあり、それぞれを吊り灯篭、置き灯篭といいます。本来は油の灯を使いますが、現在はほとんどが電球の光です。
瓔珞(ようらく)
打敷(うちしき)
位牌(いはい)
法名軸(ほうみょうじく)
過去帳(かこちょう)
数珠・念珠(じゅず・ねんじゅ)
上卓(うわじょく)
前卓(まえじょく)
経典(きょうてん)
経机(きょうつくえ)
経本のほかに、おりんや数珠、前香炉(線香用の香炉)、線香立てなどを置いたりもします。
霊具膳(れいぐぜん)
飯椀、汁椀、壺椀、平椀、高坏の五種類からなり、肉や魚を避けた精進料理が使われます。
*浄土真宗ではお供えをしません。
各宗派別の仏具と飾り方
それぞれひとつずつ揃えたものを「三具足(みつぐそく・さんぐそく)」といい、本尊に向かって左側に花立て、真ん中に香炉、右側にろうそく立てを置きます。
香炉ひとつに、ろうそく立て・花立てを一対ずつ揃えたものを「五具足」といいますが、近年では、香炉・ろうそく立て・花立てに、仏飯器と茶湯器を加えた五つで「五具足」と呼び販売しているケースもあります。
*「具足」とは、本来は甲冑(かっちゅう)や鎧(よろい)など頭胴手足の各部を守る装備のことですが、仏事では、仏壇に飾る仏具一式のことをいいます。
仏具は基本的に、三具足か五具足あれば十分ですが、そのほかにもあると便利な仏具もあります。(十一具足まであります)
お店では「〇点セット」と書かれているところもあり、また宗派によって使う数も違いますので、お店と相談して決められるとよいでしょう。
宗派別で使われる仏具
浄土真宗の仏具
また、本尊の近くに置く花立てのことを華瓶(けびょう)といい、ご先祖ではなく本尊を敬うために供えます。
華瓶には生花も造花も挿さず、樒(しきみ)という香木や青木を挿します。浄土真宗の考えでは、極楽浄土には清らかな水があふれているため喉が渇くことはない、とされるため華瓶の水を香水(こうずい)として供えています。
天台宗、真言宗、浄土宗、曹洞宗、臨済宗
日蓮宗
ただし、木魚や木柾は家庭の仏壇には置かないことの方が多いです。
仏具の飾り方
まずは本尊仏壇の最上段の中央にまつります。そして本尊の両脇に脇侍(きょうじ・わきじ)をまつります。
*脇侍本尊の左右に控える菩薩や明王などのこと。
位牌は本尊を隠さぬよう、左右か一段低いところに置きます。
次の段には中央に仏飯器・茶湯器を置き、左右に高坏を置きます。
最下段で三具足(香炉・ろうそく立て・花立て)や五具足を置くのが一般的です。
各宗派の本尊と脇侍
天台宗
脇侍右に天台大師、左に伝教大師(最澄)
真言宗
脇侍右に弘法大師(空海)、左に不動明王
浄土宗
脇侍右に善導大師、左に圓光大師(法然)
浄土真宗
脇侍右に親鸞聖人(または十字名号「帰命尽十方無碍光如来」)、左に蓮如上人(または九字名号「南無不可思議光如来」)
臨済宗
脇侍右に達磨大師、左に各派開山(無相大師、大覚禅師、仏光国師、大明国師、円明大師、正燈国師、大通禅師、聖一国師、夢窓国師、栄西禅師、大円禅師、大灯国師、聖光国師)
曹洞宗
脇侍右に承陽大師(道元)、左に常済大師(瑩山)
日蓮宗
脇侍 右に鬼子母神、左に大黒天(左右入れ替わる場合もあります)
法要とお参り
打敷は、すべての宗派で使用しますが素材もさまざまです。
季節により夏用、冬用と使い分けるのが望ましいです。安価なものから西陣織など高価なものまでありますが、中陰中の四十九日までは白無地の打敷を用います。
逆三角形と四角形があり、逆三角形は主に浄土真宗で用いられ、「三角打敷」と呼ばれます。
お参りの仕方は、まず仏壇前に正座して本尊に一礼します。次にお供え物をし、ろうそくに火を灯して線香をあげて合掌します。最後はろうそくの火を消して一礼し、下がります。
日々のお参り(おつとめ)と法要の時と、使われる仏具や作法は少し異なります。
仏具の修理と買い替え
そんな時は、修理専門の業者へ見積もりを依頼したり、新たに買い替える必要があります。
見積もりの時に修理が不可能である場合もありますので、仏具に深い思い入れがある場合は手元へ残し、買い替えたほうがお得であったり気持ちも新たに向き合えるという意味では、修理ではなく買い替えるという考えもあります。
大事なのは、私たちの家と同じように仏壇も小さな仏様のお家と考えれば、使われる仏具もせっかくならいつも綺麗な状態で日々気持ちよくお参りできるといいですね。
仏具の処分方法は?
木製のもの、金属製のもの、燃えるか燃えないか、資源再利用が可能かどうかで分別をします。そして各自治体の方法で処理をします。
本尊や掛け軸、位牌、過去帳、遺影などは魂が入っているので、魂抜きをしてもらいますが、仏具は対象ではないのでその必要はありません。
しかし、仏具とはいえ自分の手で処分するのも忍びない、という方は専門の業者へ依頼することもできます。また、ご住職に供養をお願いしてもらえば、感謝の気持ちと共に気持ちも楽になるでしょう。
仏具購入のおすすめ仏壇店
まずご自身の宗派を確認→仏壇に入るサイズを確認(仏壇がなければ、置けるスペースの確認)→予算、個人の意向を考慮→お店へ(時間が取れない方は通販など)
と大体こういう流れになります。
悲しいお気持ちの方はお辛いでしょうが、きちんと供養されるために、確認されてからの来店が大事かと思います。
ほとんどの仏壇店は、基本的な三具足は認識の通りの品ぞろえですが、五具足あたりからセット内容も変わってきているお店もあります。
「〇具足」だからこれで大丈夫だろうと勝手な判断はせず、セット内容をきちんと確認することが重要です。
2~3店舗は足を運び、それぞれのお店の特徴や雰囲気など、何かあったときにすぐ相談できる「かかりつけの仏壇仏具店」を探されるのもいいですね。
仏具の生産で有名な所
仏具を選ばれる際にまず知っておくのもよろしいかと思います。
高岡仏具
高岡銅器を使って作られる仏具はとても味わい深い作りになっています。
そのほかにも、鉄、ステンレス、亜鉛合金などさまざまな材質や製造方法で作り出されています。
京仏具
各宗派100以上の総本山、3,000余の寺々や数多くの国宝・文化財に囲まれた環境の中で、優れた技術と品質が備わっていることが大きな特徴です。
木工、金工、漆工などあらゆる技術を駆使し、細かい分業にもとづく手作りのため、全国はもとより海外での評価も高く、広く納められています。
京念珠
京念珠は、京念珠製造師という特別な資格を持った職人が、昔ながらの技法にのっとり手掛けられた製品のことをいいます。
京都では、成人のお祝いに念珠を贈る習わしがあり、慶事としてとても縁起の良いものとされています。
堺線香
線香の香料の調合は、室町時代に発達した香道、茶道の影響を受けて大いに進展しました。
仏事用の線香は、500円~30,000円と幅広くあります。
まとめ
見た目や名前が同じ仏具でも、お店によっては値段に差がありすぎる所もあるので、疑問に思ったときはご自身で生産地を確認されることが大切です。