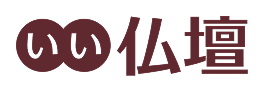神徒壇(祖霊舎)とは?祀り方やお参りの作法を紹介

神徒壇(祖霊舎)とは、先祖や故人の御霊が宿っている霊璽(御霊代)を家庭で祀っている祭壇です。仏教の仏壇にあたるものが神道では神徒壇(祖霊舎)とされており、神徒壇(祖霊舎)は御霊舎、祭壇宮、霊床、霊棚とも呼ばれています。
神徒壇(祖霊舎)とは
神徒壇(祖霊舎)は祖先の魂の依り代である霊璽(御霊代)と神具を納めている祭壇で、ほとんどが桧や栓、ビバ、欅などの素材を使い、木目が美しい白木造りで作られています。
神徒壇(祖霊舎)の購入を検討している 場合は小型、上置型、台付型、地袋付型と豊富な種類の中から毎日参拝しやすいタイプを選び、霊璽(御霊代)を神職にお祓いしてもらう「五十日祭」までに準備を済ませておきます。
安置に関しては南向きか東向き、東南向き、神棚よりやや低い位置とすることが重要です。白木を傷つけないように優しくハタキをかけてホコリをとる程度のお手入れも日々欠かさず行いましょう。
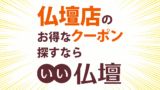
霊璽(御霊代)の意味
仏教で言う位牌を指しているのが霊璽(御霊代)です。神道では先祖や故人の魂である祖霊のよりしろである霊璽(御霊代)を神徒壇(祖霊舎)の中に置き、お祀りすることによってその魂が守護神となり家を守ってくれるという考えがあります。
神聖なもののため、霊号の書かれた霊璽(御霊代)を神徒壇(祖霊舎)に納める際は覆い(鞘)をかぶせて神徒壇(祖霊舎)の中央奥、内扉の中に安置します。霊璽(御霊代)を納めたら内扉は外から見えないように閉めておく、もしくは戸張といった幕をかけておきます。
神徒壇(祖霊舎)の祀り方
神鏡・勾玉・剣の三種の神器に加えて米、塩、水、酒、榊をお供えします。季節にとれる食べ物や故人の好物、生花などをお供えしても良いでしょう。榊以外のお供えものは毎日替えて、榊は毎月1日と15日に新しいものに取り替えるようにします。
神徒壇(祖霊舎)のお参りの仕方
神社に参拝するときや神棚へのお参りと同様に、二度お辞儀をしたあとで二度拍手、その後一度お辞儀をする「二拝・二拍手・一拝」でお参りをします。崇敬している神社によっては「二拝・二拍手・二拝」というところもあるようです。神徒壇(祖霊舎)へのお参りは神棚に参拝したあとでおこないます。